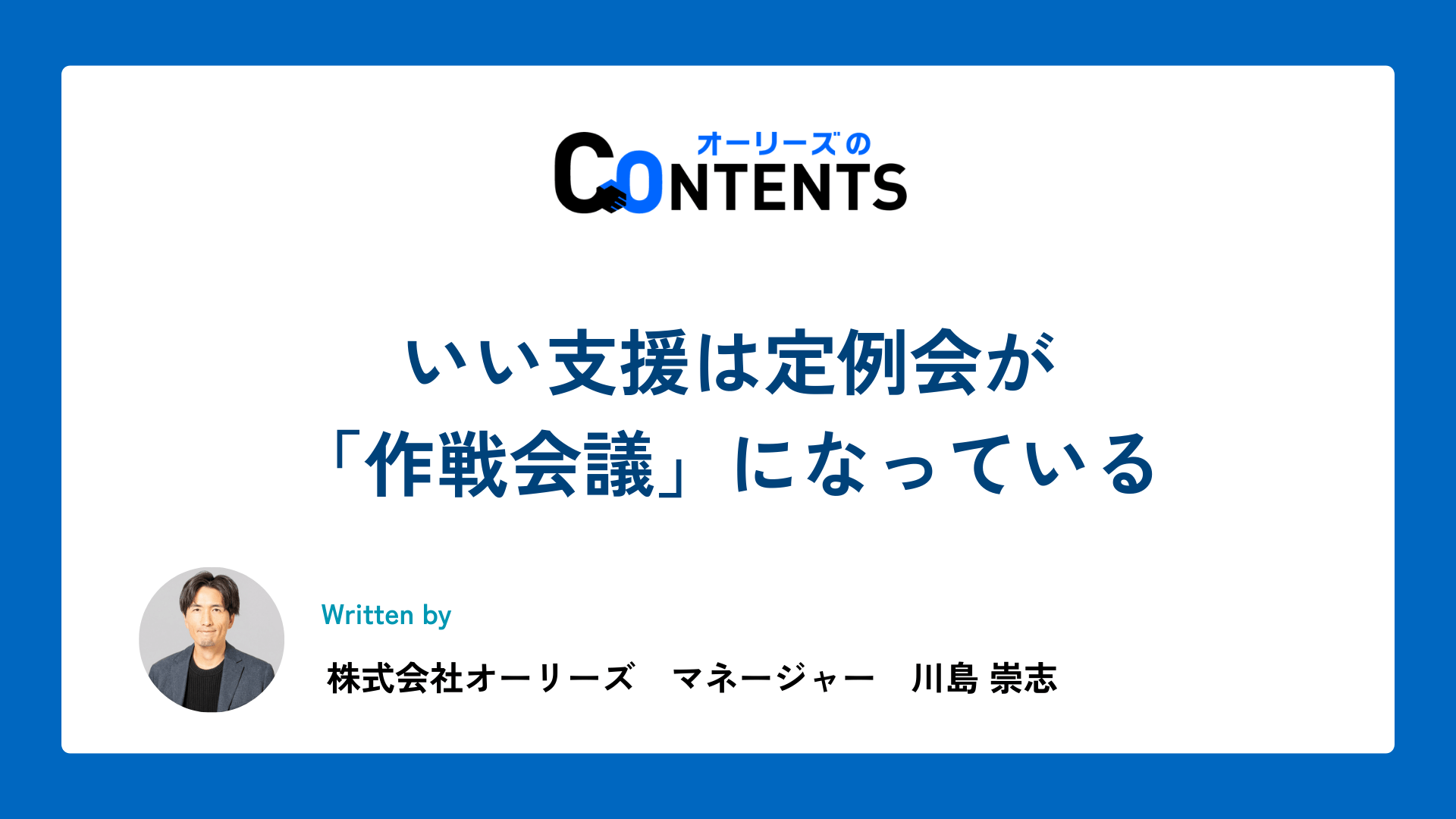いい支援は定例会が「作戦会議」になっている
広告代理店のマネージャーとして様々なプロジェクトを見ていると、「クライアントと良い関係性を築けているな」と感じる支援には、ある共通点があります。
定例会の場が、報告会ではなく「作戦会議」になっているんです。
報告よりも「議論」の時間をふやす
私たちオーリーズは、「まるで内製のような外部支援」を事業コンセプトに掲げています。「NPS経営」や「分業しない組織づくり」を通じて、クライアントに「社内チームの一員」のように感じてもらえる支援を目指しています。
一方で、現場レベルで私がメンバーに繰り返し伝えているのは、「報告よりも議論の時間を増やそう」というメッセージです。
大事なのは「報告」ではなく、新たな仮説を生み出して次のアクションにつなげることです。報告が定例会の大部分を占めていると、議論の時間が減り、打ち手の実行がどんどん後ろ倒しになってしまいます。
だから理想は、私たちはもちろん、クライアントのご担当者も、すでに数字情報が頭に入っている状態で定例会に臨むこと。
定例会の場は、「事実」ではなく「課題」からスタートして、一緒に考察を深めたり、打ち手に対して議論することが重要だよと、日頃から伝えています。
“顧客を見るな、顧客が見ているものを見よ”
私がこのような姿勢で支援に向き合う背景には、副代表の言葉があります。
「クライアントを見るな、クライアントが見ているものを見よ¹」
実際、私が担当したクライアントに、オーリーズとの取り組みを振り返って印象的だったことを質問したとき、こんな言葉をもらいました。
オーリーズさんの支援で特に印象的だったのは、「施策の実行を優先したいので、レポートはこのくらいシンプルで問題ないでしょうか?」と、数字状況の伝え方について、丁寧にすり合わせをいただいた点です。
私たちは本質的なコトに向かいたいので、詳細な報告よりも、打ち手の議論に時間を使いたいんです。 レポートを読み上げるのではなくて、すぐに作戦会議に入れるのが、オーリーズさんの良いところですね。
多くのクライアントが求めているのは、体裁の整った報告書ではなく、次のアクションにつながる議論です。
それなのに支援側が「見栄えの悪い報告書だとマズイのでは?」と勝手に遠慮しているのは、「顧客が見ているもの」を見ていない証拠です。
大切なのは、顧客と同じゴールを見ること。発注者・受注者という隔たった関係ではなく、「同じチームとして」コミュニケーションする。そうすると、自ずと本質的な打ち手を打てるようになります。
時にはクライアントと意見がぶつかることもあるかもしれません。でも、建設的で熱をもった議論ができているなら、それはいい状態だと言えます。
個人的な経験としても、そういうスタンスで顧客に向き合うほうが良い結果につながることが多いです。
作戦会議の土台は「信頼」
私は、作戦会議の土台には、信頼関係があることが絶対条件だと思っています。信頼がない状態では、一つ一つの報告に詳細な説明が求められ、小さな意思決定のたびに承認を取らなければならない。
これでは、お互いが対面に座って課題と解決策を交換し合うような「業者」と「クライアント」の関係²に陥ります。
そうなると、定例会は、施策を提案して評価される場、アイデアを出して承認してもらう場になってしまいます。
でも信頼があれば、その関係を超えられます。横に並んで座り、一緒にゴールを見る。正面から「クライアントを見る」のではなく、「クライアントが見ているものを見る」パートナーになれます。
そうなると、対等な立場で「次はこれをやってみよう」と一緒に考えられる。任せてもらえるから、細かい報告や承認プロセスは最小限になり、その時間を本質的な議論に充てられます。これが作戦会議です。
そしてこの信頼関係は、日々の行動の積み重ねで生まれます。踏み込んだ議論を重ね、一緒に考えた打ち手を実行し、成果を出す。
すると、より大胆な施策も任せてもらえるようになり、作戦会議はさらに活発になります。この好循環こそが、受発注の関係を超えたチームを作ります。
いい支援は、定例会が作戦会議になっている。その実現に必要なのは、顧客と同じゴールを見て、信頼を積み重ねていく姿勢です。
¹ 副代表足立の記事最高のクライアントワークを実現する仕組みと原理 ~アジャイルなマーケティングチームを目指して~より抜粋
² 「対面関係ではなく、並列関係」という考え方については、「業者」ではなく「パートナー」でいるために ~クライアントとの信頼関係を深めるコミュニケーションの技術~で紹介しています。また、アナグラムさんの記事でも対面ではなく横に座ることの重要性について触れられています。