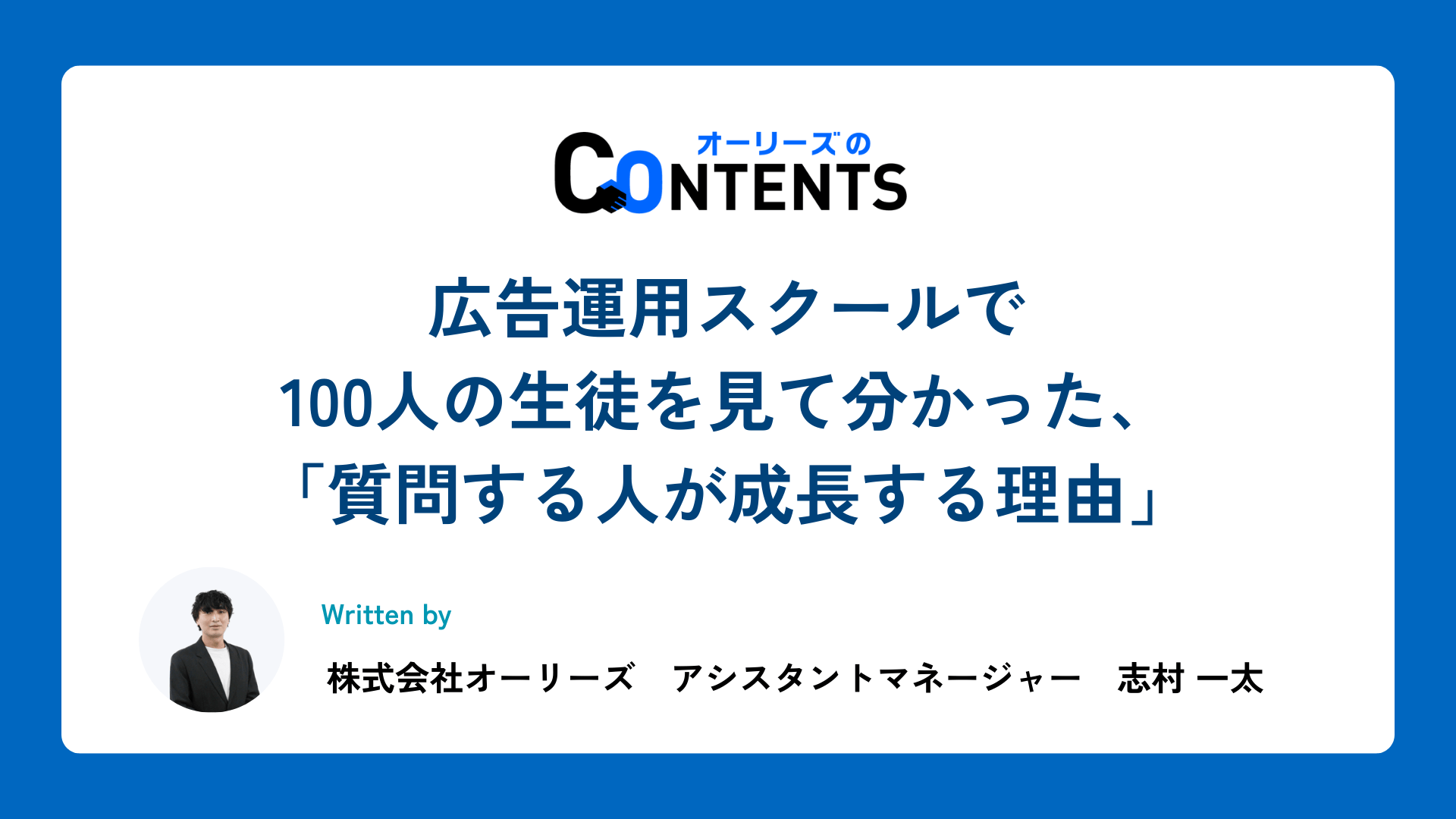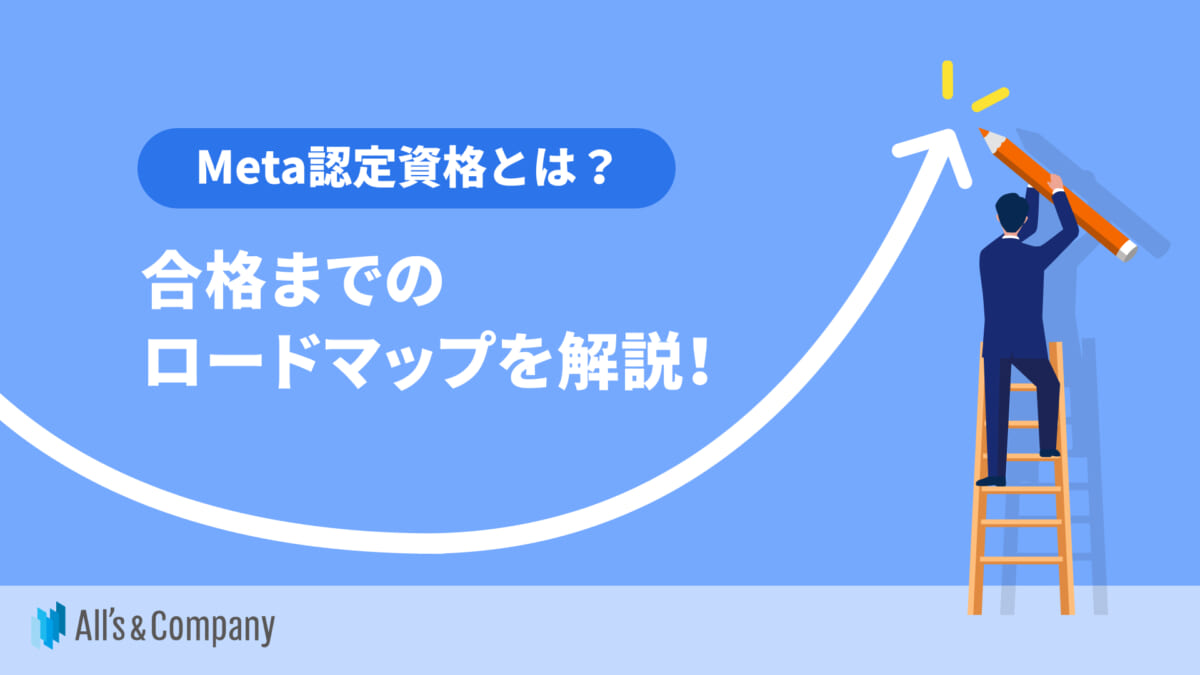- ナレッジ・ノウハウ
- 志村 一太
Meta広告の運用ベストプラクティス
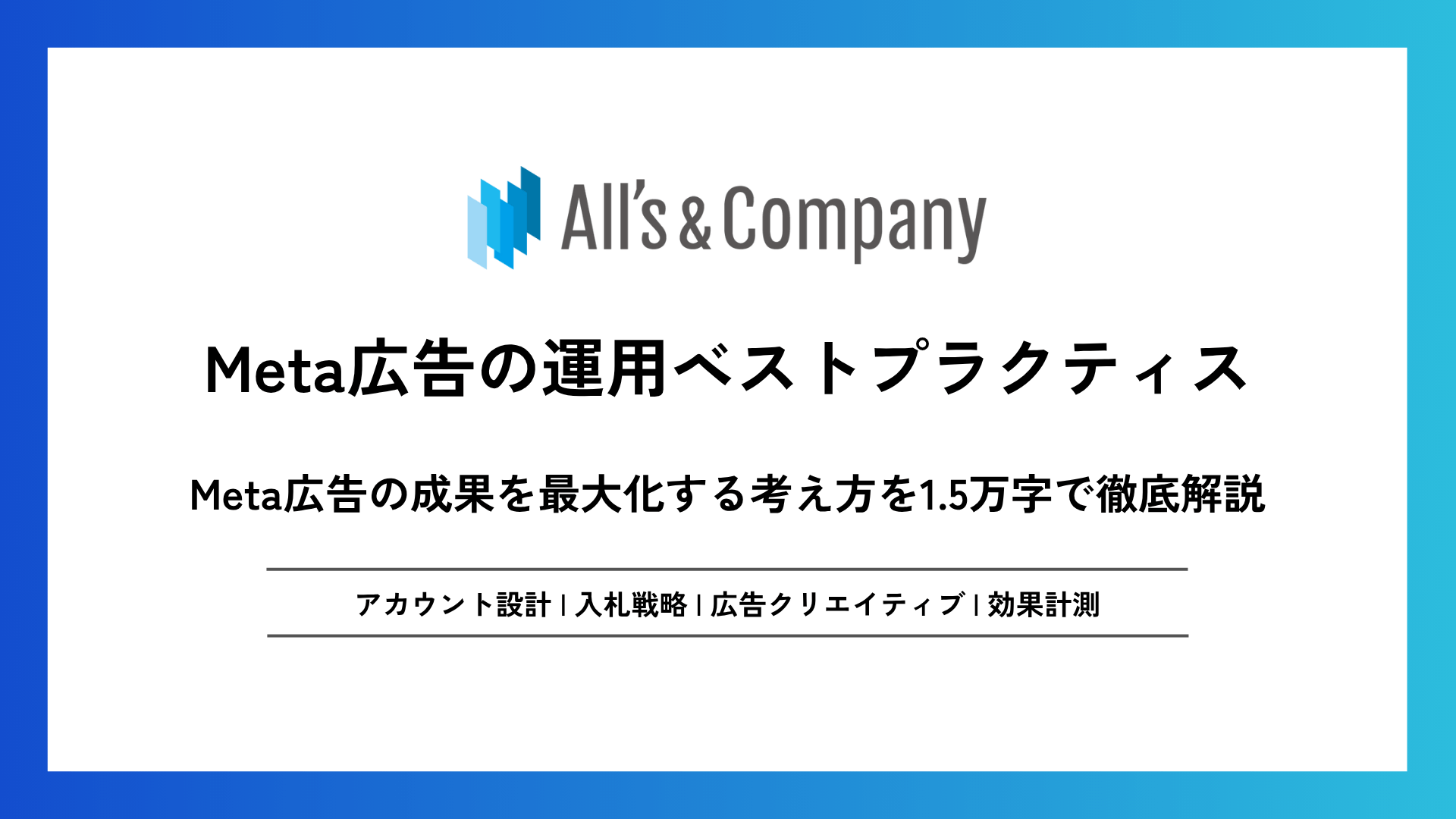
Meta広告は、多くの企業が活用する主要なSNS広告メニューである一方で、運用成果に伸び悩みを感じるケースも少なくありません。
- アカウント運用を正しく出来ているのか不安
- Meta広告の豊富な機能を活かしきれていない
- クリエイティブの評価軸があいまいで、改善の打ち手に迷う
上記のような悩みを抱えている方に向けて、Meta広告の活用頻度が高く、成果への寄与度も大きい項目にフォーカスし、広告運用者10人中8人が「そうした方がよい」と答えるレベルの共通解をまとめました。
網羅的に項目を列挙するだけではなく、読者の方が要点を理解できるように「なぜその項目を推奨するのか?」の背景・根拠も含めて解説しています。
自社アカウントに落とし込める「実行可能な運用の型」として、アカウント設定の見直しや運用改善の参考にご活用ください。
なお、本記事でご紹介する各機能については、あくまで記事公開時点での情報を掲載しているものであり、媒体の機能開発によってアップデートされる可能性があります。
詳しい仕様について理解を深めたい方は、Metaの公式ヘルプページをご確認ください。
Meta広告の出稿・成果改善なら
スピーディーな実行と検証力が強みの「オーリーズ」
オーリーズでは100社以上の支援実績をもとにMeta広告の特性にあわせた運用ノウハウを発信しています。
アカウント設計から成果改善までお気軽にご相談ください。
【広告成果を最大化するオーリーズの特徴】
- 顧客の課題にコミットするため、担当社数は最大4社
- 運用者=顧客窓口だからスピーディーな仮説検証が可能
- 顧客の半数以上が「強く」おすすめしたいと評価
Meta広告の全体像
Meta広告の運用ベストプラクティスについて詳細をお伝えする前に、Meta広告の前提情報をまとめました。
Meta広告の運用経験が長い方には既知の内容が多いと思いますので、次の章(Meta広告の運用ベストプラクティス)から読み進めてください。
Meta広告とは?
Meta(旧Facebook)広告は、FacebookやInstagramなどのプラットフォームを活用し、視覚的な訴求力と高精度なターゲティングを両立できる広告媒体です。
ブランドや商品の認知拡大に適しており、成長途上の企業にとっても活用しやすいのが特長です。
- 静止画・動画・カルーセルなど多様なフォーマットによる高い視覚訴求力
- 興味・関心・行動履歴をもとにした精度の高いターゲティング
- 自動入札やA/Bテストなど運用効率化機能の充実
- 比較的少額から始められるため中小企業でも導入しやすい
他のディスプレイ・SNS広告と比べ、限られた予算でも成果を最大化しやすい点で、多くの広告主に選ばれているメジャー媒体です。
Meta広告のアカウント構造
前提として、80点レベルの運用をおこなう上では、Meta広告のアカウントの全体像を理解し、各アカウント階層でどのような機能が利用できるのか理解しておくことが重要です。
Meta広告のアカウント構成は基本的にGoogle広告と同様なので、すでにGoogle広告を配信した経験のある方には馴染みのある構成かもしれません。(Google広告で言う「広告グループ」の階層がMeta広告では「広告セット」という名称になっています)
上記はMeta広告の各階層で設定できる主要な項目を並べたものですが、80点レベルの運用を目指す際は、まずどの階層でどういった機能が設定し得るのか理解しておきましょう。
Meta広告の運用ベストプラクティス
ここからは、Meta広告の運用ベストプラクティスを各項目に沿って解説していきます。
1.アカウント設計
Metaはディスプレイ広告であるため、検索広告のようにユーザー自らの検索トリガーではなく、web上の膨大なユーザー行動をもとに広告配信を判断しています。
そのため、その判断のもととなる機械学習が重要で、機械学習を最大限活かすためには、学習データの良質さを保ちつつ、CVデータの適正量を安定的に供給することが重要です。
それらを守るためには、アカウント設計の段階で機械学習をワークさせるような構成にすることが必要不可欠です。
上記の観点を踏まえたアカウント設計の推奨設定について、詳しく解説していきます。
⑴広告セット単位で十分なCV量を確保できるようなアカウント構成にする
運用型広告では入札単価や配信する広告の決定に機械学習の技術が利用されています。
Meta広告は他のSNS広告に比べて比較的機械学習が優秀だと言われてはいますが、極端にCV数が少ないと機械学習がワークせず、期待するほど成果が上がらない可能性があります。
では具体的にどれぐらいのCV数を確保すべきなのか?と疑問を持つ方もいらっしゃるかと思いますが、結論から言えば、Meta社から明言されているわけでは無いため断言ができません。
しかし、それではアカウント構成を検討する上での基準が曖昧になってしまうため、媒体社のヘルプページや過去資料をもとに「Meta広告の機械学習をワークさせるために必要なCV量」の判断基準となるような情報をご紹介します。
まず、Metaの公式ヘルプでは、1週間に50件のコンバージョンを担保することが推奨されており、これを下回ると、Meta広告の機械学習効率が阻害される旨が記載されています。
コンバージョン数を最大化する際は、1週間に50件以上発生するコンバージョンを選択することをおすすめします。この件数が確保されないと、Facebookのシステムが情報収集を十分に行えません。
引用:コンバージョン最適化のトラブルシューティング
また、Meta広告ではキャンペーン単位だけでなく広告セット単位で機械学習が行われているため、1広告セットあたりで週50件以上のCVを担保できるようにアカウント設計をする必要があります。
そのためユーザーコミュニケーションや予算の観点も含め、広告セットを分割する合理的な理由がなければできるだけ広告セットはまとめておき、シンプルなアカウント構成にすることをおすすめします。
⑵広告本数は2~6本で配信する
広告セット内で配信する広告の本数は絞り、1つ1つの広告に学習データを蓄積させることが重要です。
配信する広告の本数が多いと、キャンペーンや広告セットで設定している予算が複数の広告に分散されてしまい、成果の良い広告に十分な予算が投下されなかったり、新規広告に対しても投下予算が小さくなり検証スピードが落ちるといったデメリットが発生します。
ASCではない通常のキャンペーン配下の広告セットの場合、ONにできる広告の本数は最大で50本あるため、一気に50本の広告をONにすることもできますが、これでは1本1本の広告に対する表示機会が少なくなり、広告の検証を難しくする原因となり得ます。
検証対象そのもののポテンシャル以外の要素によって検証が成り立たなくなることを回避するため、あくまで目安ではありますが、広告本数は2~6本程度で配信することを推奨します。
そのため学習を統合させる観点に加えて、バナーの検証スピードも担保させる意味で、筆者は2~6本(統合させすぎず、細分化させすぎない本数)で運用することが多いです。
⑶ASCキャンペーンの活用
MetaがAIを活用してパフォーマンス向上を促す実証済みのベストプラクティスをAdvantage+ソリューションと呼びます。
Advantage+ソリューションには様々なプロダクトがあり、その中でもAdvantage+ Salesキャンペーン(通称ASC)はキャンペーンの自動化を促進し、広告成果を最大化させられる注目のプロダクトです。
Advantage+Salesキャンペーンは以下3つのプロダクトで構成されています。
①Advantage+オーディエンス
顧客に関する広告主の知識とAIを組み合わせ、最も関連性の高いオーディエンスにリーチする機能です。
例えば野球帽をMeta広告を活用して販売する場合、広告主は野球帽を購入してくれそうな顧客像を思い浮かべ、以下をオーディエンス設定するとしましょう。
- 男性
- 18~35歳
- 1度ウェブサイトに訪問したことがあるユーザー
- 野球とランニングに興味がある
Advantage+オーディエンスをオンにすることで、このオーディエンス設定に加えてAIが以下のようなユーザーにも広告を配信します。
- 男性、50歳、庭いじりをするときに被る帽子を探している
- 女性、DJをするときに被る帽子を探している
- 女性、戸外で子どもと遊ぶときに被る帽子を探している
このように広告主が「こういったユーザーに配信したい」と設定したオーディエンス設定の外にも、商品やサービスに興味を持っているユーザーは多く、そういったユーザーをAIを活用して判別、配信してくれます。
Advantage+オーディエンスを設定する際は、広告セットの編集から「おすすめの設定を使用する」を押すことでONにすることができます。
②Advantage+配置
配置を自動化することで、全体で最も費用対効果が高くなるように各配置へ入札します。
例えばFacebookのみに配信するよりも、Facebook・Instagram・Messenger・AudienceNetworkすべてのプラットフォームに配信するほうが、商材・サービスや儒供給の変化に合わせて、入札をタイムリーに調整してくれます。
Advantage+配置は広告セットの編集から、「プラットフォーム」で全てのプラットフォームにチェックをつけることでONにすることができます。
ただし中にはどうしても配信したくない配置があるケースも出てくるかと思います。
その場合、Advantage+配置をオンにしなくても、キャンペーンで配置を6つ以上使用することで成果最大化に繋がるので、なるべく多くの配置に配信するようにしてみてください。
配置は広告セットの編集から「プラットフォーム」の「配置の制御」で、配信させたくない配置を押して「-」に切り替えると配信を制御できます。
③Advantage+予算
キャンペーンで設定された予算を最良の機会に配分することで、パフォーマンスの最大化を図る機能です。
Advantage+予算では、キャンペーンの予算をその配下の広告セットに対して、適切な配分で分けて広告を配信してくれます。
- キャンペーン・10万円/日
- 広告セットA・CPA1,500円:5万円/日
- 広告セットB・CPA2,500円:3万円/日
- 広告セットC・CPA3,000円:2万円/日
上記のように各広告セットの成果を考慮し、キャンペーン全体でCPAが低くなるような予算配分を行います。
これにより手動で予算を配分する必要がなくなるのと、タイムリーに成果を配信に反映させることができます。
Advantage+予算を使用する場合は、キャンペーンの編集から「予算戦略」で「キャンペーンの予算」を選択することで設定できます。
Advantage+予算は成果をシビアに評価し、予算配分に反映させる傾向があるため、成果によっては特定の広告セットに予算が集中し、予算コントロールが難しくなる場面があります。
その際は各広告セットの編集から「1日下限」「1日上限」のどちらかを設定することで、その広告セットで配信される下限/上限日予算を設定することができます。
機能としては下限/上限どちらも設定することができますが、両方設定すると調整幅が小さくなりAdvantage+予算が十分機能しなくなる可能性があります。
そのため機能によってはONにできないアカウントもあるかもしれませんが、ONにできるものから積極的に取り入れることでMetaの最新のAIソリューションを広告配信に活用できます。3つすべてONにすることで成果最大化に繋がるため、基本的にはONにするスタンスで導入してみましょう。
2.入札戦略・ターゲティング
続いて、入札戦略・ターゲティングに関するベストプラクティスを解説します。
⑴広告配信の目的に応じて入札戦略を選択する
CPA・ROASや獲得件数など、「何が達成できれば良いのか」を定義した上で、その定義に則した入札戦略を選択しましょう。
- 消化金額に基づくもの
- 目標に基づくもの
- 手動(入札価格上限)
Meta広告では手動(入札価格上限)の運用難易度は高く、一般的に使用する機会が少ないため、ここでは「消化金額に基づくもの」「目標に基づくもの」の2つの入札戦略のセグメントについて説明します。
まず消化金額に基づく入札とは、予算全額を消化して可能な限り多くの結果とバリューを得ることに集中する戦略です。
メリットとしては予算全額を消化することを第一の目的に置くため、日の配信金額のコントロールが容易であることが挙げられます。
そのため、突然日の配信金額が縮小したり、設定した日予算を大幅に超えて配信されるアンコントローラブルな事象は発生しづらいです。
一方でデメリットは、CVを獲得できる見込みのあるオーディエンスがいなかったり、成果の良い広告がなくても、とにかく設定した日予算を消化しようとするためCPAのコントロールが難しいことが挙げられます。
消化金額に基づく入札は、広告セットの「コンバージョン」の設定項目で「結果の単価目標」を入力できる欄がありますが、こちらを空白にすることで設定できます。
次に目標に基づく入札とは、達成したいCPAやROASを設定することで、その目標を守ることに集中する戦略です。
達成したいCPAを設定する戦略を「結果の単価目標」と呼びますが、これはマーケットの状況に関係なく設定されたCPA付近に維持するように配信しようとします。
メリットはCPAのコントロールが容易であり、仮にCPAが目標より上昇していた際は設定している単価目標を引き下げることでコントロールできます。
デメリットは単価を設定したCPA付近に維持することを1番の目標とするため、CVしそうなユーザーがいない場合は設定した日予算を大きく下回って配信金額を縮小させることがある点です。
獲得のポテンシャルが低いと媒体に判断されると、設定した日予算の1%ほどしか配信金額が出なくなりますが、この際は設定している単価目標を引き上げるか消化金額に基づく入札戦略に切り替えましょう。
また目標に基づく入札の中でも、もう一つ「ROAS目標」で運用することも可能です。ROAS目標とは結果の単価目標のROASバージョンと考えてよいです。
結果の単価目標の設定は、入札戦略を「単価の目標」にし、「結果の単価目標」の欄に希望する目標CPAを設定します。
ROAS目標は広告セットの編集から、パフォーマンスの目標を「コンバージョン数の最大化」に設定することで、目標とするROASを入力する箇所が表示されます。箇所箇所に目標ROASを入力すれば設定可能です。
⑵高頻度の運用調整や大きな調整は避ける
Meta広告の学習を最大限活かすためには、高頻度の運用調整や大きな調整は避けるのがベターです。
例えば運用調整の頻度だと、筆者の場合、広告セットの学習を考慮する際には、広告のON・OFF、日予算やtCPAの調整は2~3日に1度を目安で行っています。(調整を入れない期間はこれよりも長くなって問題ありません)
これは調整を入れない期間を入れることで、媒体の学習を進める意図があります。
また、可能な限り大きな調整も避けたほうが良いです。
例を挙げると、日予算の増減幅は+-20%までが推奨されています。
他にも広告セット内の広告をOFFにする際には、該当の広告の配信割合が30%以上だと大きな調整にあたるため要注意です。
OFFにしたい広告のシェアが30%ある場合、OFFにしてしまうとその広告セットの学習の30%が失われることになります。
そのため配信割合が高い広告をOFFしたい場合は、なるべく新規広告や過去の当たり広告をONにし、該当の広告の配信割合が30%以下になった頃合いを見てOFFしましょう。
⑶リターゲティング/類似/興味関心/ブロードは一通り検証する
Meta広告では広告セットでターゲティングの設定ができ、主なターゲティングの種類にはリタゲーティング/類似/興味関心/ブロードがあります。
また、設定方式としては、1つの広告セットに1つのターゲティングを設定する方法と、1つの広告セットに複数のターゲティングを設定する方法の2種類があります。
1つの広告セットに1つのターゲティングを設定する場合は、複数のターゲティングを別々に検証することができるため、そのアカウントにおいて最も成果を最大化できるターゲティングを明確にすることができるのがメリットです。
デメリットは、複数のターゲティングを同時に配信する際は、広告セットをターゲティングの数分用意する必要があるため、細分化構造になりやすくなることです。
そして1つの広告セットに複数のターゲティングを設定する場合のメリットは、統合構造になることや複数のターゲティングを組み合わせて配信できることから成果が最大化されやすくなることです。
デメリットは仮に設定したターゲティングで成果が上がった場合、どのターゲティングが成果にどんな影響を与えたのかを可視化しにくくなるため、再現性がないことが挙げられます。
おすすめなのは、1つの広告セットに1つのターゲティングを設定して検証を進めることです。
ただし予算規模等の兼ね合いから複数の広告セットを用意できない場合もあるため、そのような際は1つの広告セットに複数のターゲティングを設定しましょう。
ターゲティングの検証優先度はCVを獲得できる確度の高いものから行った方がよいため、リタゲーティング→類似→興味関心→ブロードの順で筆者は検証することが多いです。(興味関心はアカウントに合うものがない場合もあり)
⑷配信初速の配置はAdvantage+配置を使用し、成果に応じて除外or切り出しで対応
配置については、配信初速はAdvantage+配置を活用しましょう。
Advantage+配置とは、Metaの配信システムにより予算を最大限に活用しながら広告の露出機会を増やし、キャンペーンの目的が売上の場合はCVを最大化させるような形で広告が配信されます。
つまりAdvantage+ 配置では、設定で利用可能なFacebook、Messenger、Instagram、Meta Audience Networkの設定で利用できるすべての配置に広告が掲載されます。
配信初速はすべての配置に配信をし、その後2週間~1か月ほど経過した段階で各配置の実績を分析しながら配信面を絞ったり、場合によっては特定の配置を切り出して別広告セットで配信する等しましょう。
配信面については以下の傾向がありますが、バイアスによって除外or切り出しての配信をするとCV獲得の機会損失に繋がる可能性があるため、必ず実績に基づいた分析をもって配置を最適化していきましょう。
-
AudienceNetworkに関しては、媒体CVを獲得しやすい傾向にあるが、LTVや商談率といった奥の指標に繋がらないユーザーが多い
- 特にお小遣い稼ぎアプリやポイントアプリへのimpが多い際は上記傾向にある
- AudienceNetworkをいきなり除外するのではなく、まずはパブリッシャーユニークでの除外対応でも良い
-
BtoB商材の資料請求CVに関しては、InstagramよりもFacebookのほうがCPAが低い傾向にある
- ただしウェビナーやホワイトペーパーなどの潜在層へリーチするための配信の場合はInstagramでも獲得できることが多いため、広告配信の目的や獲得したいユーザーのファネルに合わせて配置を選びましょう
- Facebookの方がビジネスユーザーが多いため、顕在層向けの資料請求CVを獲得しやすい傾向にある可能性がある
3.クリエイティブ
Meta広告は様々なクリエイティブフォーマットと複数の設定可能な項目により、多彩なユーザーアプローチが可能です。
直近のトレンドも押さえながら正しい形の検証を繰り返すことで、CVを最大化させる「当たりクリエイティブ」の発掘ができます。
⑴フォーマット網羅
Meta広告では様々なフォーマットのクリエイティブを配信することができます。
- 静止画
- 動画
- カルーセル
Meta広告では、これらのフォーマットはミックスさせた状態(常にすべてのフォーマットの広告が配信されている状態)で配信することを推奨されています。
理由としては、FacebookやInstagramには静止画と動画、それぞれに反応しやすいユーザーが存在しており、仮に静止画しか配信していなかった場合は、動画に反応しやすいユーザーへのオークションに勝ちづらくなるためです。
結果として特定のフォーマットしか配信していない広告セットのCPMが上昇しやすくなり、成果悪化に繋がる可能性があります。
また動画を配信する際には、Meta広告でトレンドとなっているUGC風の縦長動画にも挑戦してみましょう。
UGCとはUser Generated Contentsの略称で
- 動画内のアングルがユーザー目線のコンテンツ
- 動画内の構成やコピーがユーザーから生成されたようなコンテンツ
といった特徴を持つものです。
このUGC風の動画を縦長サイズ(1080×1920ピクセル)にすることで、直近広告在庫が増えているInstagramのストーリーズ・リールにいるユーザーにアプローチすることが可能です。
⑵サイズ網羅
バナーのフォーマットを網羅させるのに加えて、それぞれのバナーサイズを網羅させることが重要です。
Meta広告では以下の画像のように、1つの広告に対して配信面ごとに別々のバナーを設定できます。
ここではデフォルトで設定しているバナーのサイズ違いを設定することで、各配信面の大きさに合ったバナーが配信されます。
これを設定することにより、ユーザーが見ている枠に合ったサイズのバナーが表示され、デフォルトサイズのバナーが表示されるよりもユーザーファーストな体験につながり、CTRが上昇する可能性があります。
これは静止画のバナーだけでなく動画でも同様に設定できるため、なるべく全てのバナーで以下サイズのバナーを用意しましょう。
- 1080×1080ピクセル(デフォルト設定)
- 1080×1350ピクセル(主にフィード)
- 1080×1920ピクセル(ストーリーズ・リール)
⑶CTA・見出し・メインテキストも検証する
Metaの広告の要素ではバナーがレバーとして最も大きいですが、その他にもさまざまな要素が含まれます。
それぞれの要素において、アカウントや成果に合わせた検証を進めましょう。
- CTA
- Meta広告のアクションを促すボタン
- 「詳しくはこちら」「もっと見る」「登録する」「ダウンロード」「インストール」等
- 例えば資料請求ダウンロードをMeta広告で獲得したい場合、「詳しくはこちら」と「ダウンロード」でどちらがCTRやCVRが高くなるかを検証する
- 「詳しくはこちら」「もっと見る」「登録する」「ダウンロード」「インストール」等
- Meta広告のアクションを促すボタン
- 見出し
- バナーの直下に表示されるテキスト。太字で表示されるため、ユーザーに目に入りやすい
- 見出しに最適なユーザーメリットを検証する
- バナーの直下に表示されるテキスト。太字で表示されるため、ユーザーに目に入りやすい
- メインテキスト
- バナーの上に表示されるテキスト。見出しよりも文字数が多く表示されるため、ユーザーメリットや商材詳細を詳しく記載できる
- メインテキスト内の冒頭はどのような訴求を持ってくると、CTRが高くなるか検証する
- バナーの上に表示されるテキスト。見出しよりも文字数が多く表示されるため、ユーザーメリットや商材詳細を詳しく記載できる
⑷広告の入れ替えは配信金額+最適化対象にしている指標の単価orステータス「広告疲れ」で判断
Meta広告にはクリエイティブの疲弊という現象があります。
これはユーザーが同じバナーを使った広告を何度も見ることにより、反応が悪くなり結果的にその広告のCPAが上昇する現象のことです。
このクリエイティブの疲弊を回避するために、Meta広告では成果が悪くなった広告を停止し、新規広告を配信開始させるPDCAが常に回っている状態であることが望ましいです。
PDCAを回すうえで、広告を停止するかどうかは「配信金額」と「最適化対象としている指標」「広告疲れのステータス」で判断しましょう。
①配信金額
Meta広告は「この広告はユーザーからのCVを集められそうだ」と判断された広告=媒体評価が高い広告は積極的に配信する傾向があります。
そのため媒体評価が高い広告は配信金額が伸長しやすいです。
逆に1週間等一定の期間配信しているにもかかわらず、配信金額が広告セットの10%に満たないような広告は媒体評価が低いと言えます。
そのような広告をいつまでも配信していても検証が進まないため、配信金額が伸長しない広告は停止しましょう。
②最適化対象にしている指標の単価
次に参考にするべき指標は最適化対象にしている指標の単価です。
例えば最適化地点に置いている指標が「登録完了」の場合、1週間等の一定期間におけるその広告の登録完了の単価(CPA)を確認し、広告セットの単価よりも極端に高くなっていれば停止しましょう。
上記判断軸で停止する広告を精査する際には、以下に注意してください。
- 最適化対象にしている指標の単価よりも先に、配信金額を見る
- でないと配信金額が1週間に300円ほどしか伸長していない広告に対して、たまたま1件ついたCVをみて「CPAが300円だから優れた広告だ」といった精度の低い精査になってしまいます。
- 各指標における精査基準は、アカウント単位で決める
- 例えば以下の精査基準は、〇内の数字を大きくすることで広告の入れ替わりスピードが落ちるため、バナーの制作本数が少ないアカウントに適しています。
- 判断日よりさかのぼって〇日間の実績で判断する
- 特定期間で広告セットの配信金額の〇%以下しか配信されていない広告を停止する
- 特定期間で広告セットの平均CPAの〇%以上CPAが上昇している広告を停止する
- 逆にバナーの制作本数が多かったり、当たりバナーがない状態であるため検証スピードを上げたい場合は、〇内の数字を小さくすることで広告の入れ替わりスピードが上がります。
- 例えば以下の精査基準は、〇内の数字を大きくすることで広告の入れ替わりスピードが落ちるため、バナーの制作本数が少ないアカウントに適しています。
③ステータス「広告疲れ」
また広告のステータスが「広告疲れ」と表示されているかどうかも、広告の入れ替えの基準にしましょう。
オーディエンスが何度も同じ広告を見たと判断された場合、広告の配信ステータスが「広告疲れ」と表示されます。
この表示は当該広告で使用しているバナーが表示された全ての場合が考慮されます。
つまり該当の広告だけでなく、すべてのキャンペーン、広告セットで配信されている同一のバナーに対するユーザーの閲覧・反応をもとにしてステータスが表示されています。
配信金額や最適化対象にしている指標の単価は、広告の成果をもとにした入れ替え判断の材料、そしてステータス「広告疲れ」は広告の疲弊度合いをもとにした入れ替え判断の材料として使いましょう。
参考:広告疲れに関するMeta広告マネージャーでの推奨事項について
4.効果計測・分析
アカウント構成の章でも触れましたが、Meta広告のアカウント成果を最大化するうえでは機械学習を十分にワークさせることが重要です。
機械学習をワークさせる上では、学習を最大化させるピクセル設定によってシグナルの学習量と質を担保することが必要です。
⑴標準イベント/カスタムイベント/カスタムコンバージョンを使い分ける
Meta広告で設置できるイベントには、「標準イベント」と「カスタムイベント」があります。
さらにイベントパラメータを標準イベントやカスタムイベントに付与することで、追加情報をイベントに付与することができ、特定の条件のイベントパラメータの値で計測された標準イベントやカスタムイベントを「カスタムコンバージョン」と呼びます。
まず標準イベントとカスタムイベントについて説明します。
標準イベントとは、Metaによって定義づけされたイベントのことであり、コンバージョンの計測や最適化、オーディエンスの作成に活用できます。
一方でカスタムイベントとは、ピクセル単位で個別に定義づけされたイベントのことです。
なるべく標準イベントを利用したほうが良い理由としては、Metaによって定義づけられている=別のアカウントやピクセルも含めたMeta全体の学習を活用できるためです。
例えば、標準イベントの一つである「登録完了」をWebサイトのサンクス地点に設置した場合、該当ピクセルにおける「登録完了」したユーザーだけでなく、Meta全体で「登録完了」したユーザーの学習も活用することができます。
カスタムイベントでも、標準イベントと同様にコンバージョンの計測や最適化、オーディエンスの作成ができますが、個別に定義づけされているためあくまでもそのピクセル内のみの学習となり、Meta全体の学習を活用することができません。
Meta全体の学習を活用できない点で、標準イベントよりもカスタムイベントを優先的に設置するメリットはほとんどありません。
そのため標準イベントを優先的に設置し、使用できる標準イベントが足りなくなった際にカスタムイベントを利用することをおすすめします。
次にカスタムコンバージョンについて説明します。
イベントパラメータを標準イベントやカスタムイベントに付与することで、カスタムコンバージョンを作成する際に必要な追加情報をイベントに付与することができますが、イベントパラメータを付与するだけでは実際にCV計測・最適化に活用することはできません。
付与したイベントパラメータの特定のルールで、標準イベントやカスタムイベントをCV計測・最適化に活用するには、カスタムコンバージョンを活用します。
カスタムコンバージョンを作成する場合は、各アカウントのイベントマネージャーへ入り、「カスタムコンバージョン」の欄で作成できます。
ルールで「Event Parameters」を選択し、今回使用したいイベントパラメータを入力、条件を選択した後に今回カスタムコンバージョンを使用して絞り込みたい文字列・整数を入力します。(上画像の例だとonkan)
これでカスタムコンバージョンを作成することで、標準イベントやカスタムイベントに付与されたイベントパラメータによる特定のルールのもとCV計測や最適化ができます。
⑵重みづけを意識したタグ設置
Meta全体の学習を活用するためには、標準イベントを設置するだけではなく、ユーザーの重みづけを意識したタグ設計が重要です。
Metaの標準イベントには、イベントに対して想定されるアクションも定義づけされています。
上記はMetaでよく使われる標準イベントと、そのイベントに対して想定されるアクション、さらにそのアクションをページ階層を意識して設置する場合に推奨される順序に並べています。
例えば、コンテンツビューというイベントのみを発火させたユーザーより、カート追加も発火させたユーザーはより奥の階層まで進んだユーザーとMetaは認識します。
そのためコンテンツビューまでよりもカート追加まで発火させたユーザーの方がMetaでは「良質」なユーザーとして学習されています。
よくサンクス地点のみにイベントを設置したり、途中の階層も一部にしかイベントを設置しない例を見ますが、広告の遷移先からサンクス地点に至るまでなるべく全ての階層にイベントを設置しましょう。
理由としては2点あります。
- マイクロコンバージョンを実装したいタイミングですぐに実施できる
- 各階層のユーザー離脱率をMeta広告ベースでも把握できる
- GAでも各階層の離脱率は把握できますが、Metaのピクセルでもシグナルを収集することでMetaの各広告ベースでの離脱率を把握できるようになり、分析に役立ちます。
ここで注意してほしいのが、意識するのは「階層」に対する順番であり、標準イベントで定義づけされたアクションではありません。
たとえば、遷移したLPからサンクスまでの導線で商品をショッピングカートに入れるアクションがなかったり、支払情報を追加するアクションがなくても、カート追加や支払情報の追加を使ってすべての階層にイベントを埋めることを推奨しています。
Metaで使用できる標準イベントには数に限りがあり、各階層で行われるアクションと標準イベントで定義づけされたアクションが必ずしも一致しないため、階層に対する順序を優先させてください。
⑶イベントパラメータを活用してCVに重みを付ける
Metaのイベントには先述の通り「標準イベント」と「カスタムイベント」があります。
イベントパラメータを利用することで、これらのイベントに対して商品のグループや価値などの追加の情報を付与することができます。
- 同じクレンジングバームでも、「しっとりタイプ」「さっぱりタイプ」「温感タイプ」等の商品のタイプ別にCV計測・最適化をかけたいとき
- 資料請求・WPダウンロード・お問い合わせなど、異なるアクションを別々にCV計測・最適化をかけたいとき
- 20,000円以上の商品を購入したユーザーに価値を付け、CVの価値の重みづけをしたいとき
イベントパラメータには以下の種類がありますが、付与できる値に制限があるものもあるためご注意ください。
| イベントパラメータ | 値のタイプ | 内容 |
|---|---|---|
| content_category | 文字列 | ページ/商品のカテゴリ |
| content_ids | 整数または文字列の配列 | SKU(Stock Keeping Unit)などの、イベントに関連付けられた商品ID |
| content_name | 文字列 | ページ/商品の名前 |
| content_type | 文字列 | 商品や商品グループ等のタイプ |
| contents | 文字列 | 商品IDや商品数 |
| currency | 文字列 | valueに対する通貨(JPY/USD等) |
| value | 整数 | 商品の価値 |
⑷詳細マッチングを実装する
詳細マッチングを実装することで、オーガニックや他広告媒体を含めたすべての流入ユーザーと、そのユーザーが使っているFacebookとInstagramのアカウントを突合することができます。
各遷移先内の導線にある入力フォームから、電話番号やメールアドレスをハッシュ化させて詳細マッチングにより媒体へデータとして送ります。
その後、媒体側で保持されているFacebookやInstagramに登録されている電話番号やメールアドレスと突合することで、アカウントを割り出しています。
これによってCVしたユーザーのFacebookとInstagramでの行動を紐づけることができるので、より媒体の学習に厚みが出ます。
また、媒体の学習を補完するため、iOS14.5以降のcookie規制の対策にもなります。
詳細マッチングには「自動詳細マッチング」と「手動詳細マッチング」の2種類があります。
自動詳細マッチングはイベントマネージャー内の「設定」で、トグルをオンにするだけで実施可能です。
このトグルをオンにすることで、入力フォームのどの部分が「電話番号」「メールアドレス」なのかを、媒体が推測し情報を拾います。
また、手動詳細マッチングはコードの記述が必要であるため、Metaの公式サイトを見ながら実装しましょう。
手動詳細マッチングはコードを記述することで、自動詳細マッチングのような推測ベースではなく、「この部分に電話番号が入力されます」といった指示を出すことができるため、自動詳細マッチングよりも精度が上がります。
自動詳細マッチングと手動詳細マッチングでは、データ突合のマッチ率が異なり、手動詳細マッチングの方がマッチ率が高いです。
自動詳細マッチングと手動詳細マッチング両方を導入することで、データ突合の精度が上がるためなるべく両方導入しましょう。
⑸CAPIを導入する
iOS14.5以降のCookieの規制に伴い、Metaでも広告配信で活用するシグナルを収集できなくなったことから、成果悪化に繋がっているアカウントもあります。
Meta広告ではCookie規制で収集できなくなったシグナルを補完するために、コンバージョンAPI(CAPI)を導入することを推奨されています。
CAPIを導入することで、サーバーやウェブサイトプラットフォーム、CRMツールから、マーケティングデータを直接Metaに接続することができます。
CAPIの連携には以下のいくつかの方法があります。
アカウントやマーケティングデータの管理方法より、最適な連携方法を選択しましょう。
-
コンバージョンAPIゲートウェイ
- コーディング不要のMetaによる連携方法であり、迅速かつ簡単に連携できる一方で、サーバーやCRMツール等で管理されているマーケティングデータをMetaに接続することはできません。
-
パートナー連携
- Adobe、GTMなどのMetaのパートナープラットフォームでウェブサイトを運営している場合は、この連携方法がおすすめです。
-
コードを使った直接連携
- 連携プロセスを細かく設定ができ、オフラインコンバージョン等をMetaに送ることができるため、CAPIでないとできない施策もできる一方で、工数は最もかかります。
まとめ
Meta広告で成果を高めるには、機械学習の特性を活かしたアカウント設計、目的に応じた入札・ターゲティング戦略、多様なフォーマットによるクリエイティブ検証、そして精緻な計測体制の構築が不可欠です。
本記事で紹介したベストプラクティスは、広告運用者の8割が「取り入れるべき」とする共通解に基づいています。自社アカウントの改善余地を見つけるチェックリストとして活用し、運用の質を着実に引き上げていきましょう。
媒体仕様の変化にも柔軟に対応しながら、継続的なアップデートを心がけることが成果最大化への鍵となります。
Meta広告で広告成果をあげるなら
スピーディーな実行と検証力が強みの「オーリーズ」
「Meta広告を始めたい」「Meta広告の成果に課題がある」なら、
広告専門のクリエイティブチームを持つオーリーズへ。
100社以上の支援実績をもとに、配信開始から成果改善まで伴走支援。
【広告成果を最大化するオーリーズの特徴】
- 顧客の課題にコミットするため、担当社数は最大4社
- 運用者=顧客窓口だからスピーディーな仮説検証が可能
- 顧客の半数以上が「強く」おすすめしたいと評価