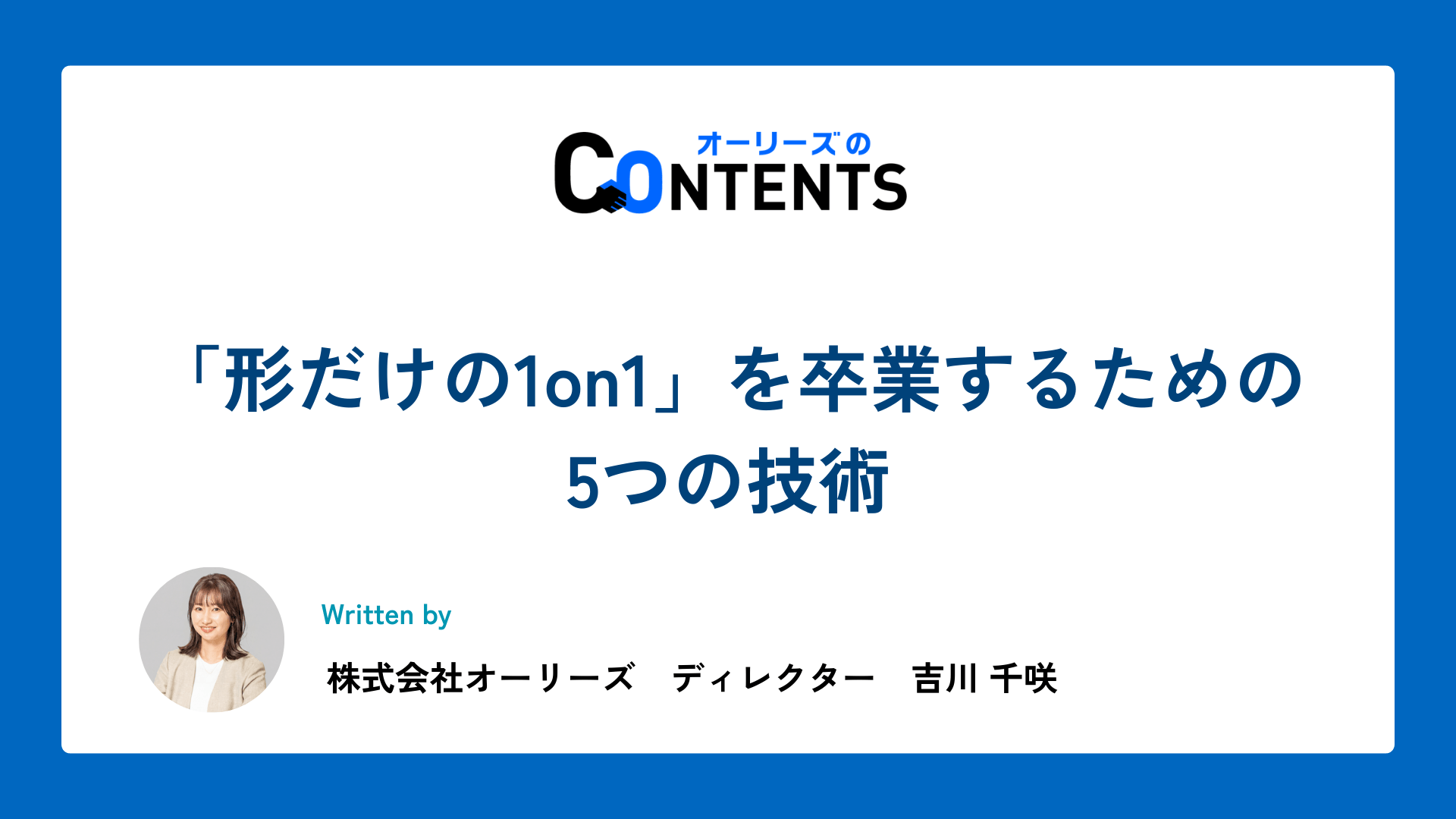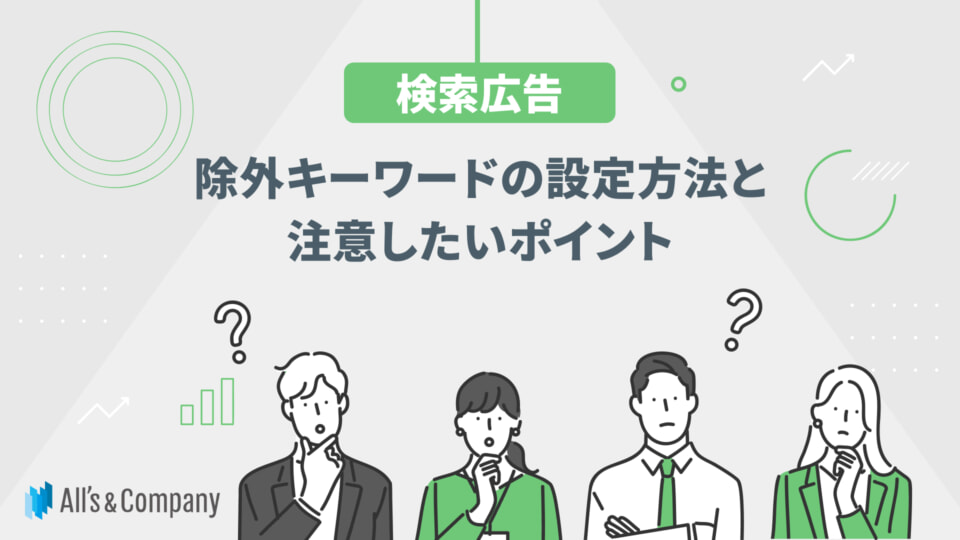「形だけの1on1」を卒業するための5つの技術
チームリーダーとして初めて1on1を担当することになったとき、メンバーに「1on1は皆さんのための場だから、話したいことは自分で決めてOK」と伝えていました。
1on1に関する書籍を読んでインプットしたし、Notionで専用のフォーマットも準備した。人との会話は得意な方なので、うまくやれる自信はありました。
目次
手なりでやればうまくいく、そんな甘い話ではなかった
でも、いざやってみると、ぜんぜん思った通りにはいきませんでした。
メンバーに記入をお願いした専用のフォーマットには未記入が多く、会話は進捗確認と雑談で終わってしまう。
「何か困ってることはある?」と聞いても「特にないです」「大丈夫です」の繰り返し。
形式的な1on1になってしまい、お互いの時間を無駄にしている感じがしました。
プロとの差は「技術」だった
そこで、私が定期的に受けている外部コーチとの対話を思い返してみました。コーチにはなんでも話せる。毎回、気持ちの整理ができている。
この差はなんで生まれてるんだろう?
振り返ってみると、プロのコーチの1on1には明確に「技術」がありました。安心感を作り出す話し方、内省を促す問いの立て方、沈黙の使い方。
即興や感覚ではなく、技術と実践によって磨き上げられたスキルです。
私は1on1を甘く見ていました。メンバーのスタンスに依存し、手なりでやればそれなりに機能すると思い込んでいました。でも実際は、技術なくして良い対話は生み出せなかったんです。
実践で身に着けた「5つの技術」
コーチの会話を参考に、まず自分にできる具体的な工夫から始めることにしました。
いきなりプロレベルは無理でも、一つずつ技術を身につけていけばいい。試行錯誤を続けるなかで、うまくいく方法が見えてきました。
テンションコントロール
相手のテンションが低いと話しにくい。だから、どんなに作業が詰まっていても、1on1の5分前から頭を切り替える習慣をつけました。
意識的に明るいテンションを作り、相手が話しやすい状況をつくる。これが意外と難しく、自然とできるようになるまでには時間がかかりました。
相手の言葉をさえぎらない
メンバーが話しているときに「いや、これこういうことだよね」と口を挟みたくなることもあります。
でもその後に大事な内容や言葉が含まれているかもしれないし、途中で遮ってしまうことでメンバーが話すことをやめてしまう。
ここをぐっとこらえて、一旦は本人の口から最後まで話してもらうようにしました。傾聴の技術は、意識的な練習なしには身につきませんでした。
言い換えの技術を習得する
「それはよくないね」「こうしないとダメだよね」といった表現は、メンバーのやる気を削いでしまいます。
例えば「せっかく頑張って○○しているのに評価されないともったいないよね。だからこういう方向性、考えてみたらどう?」のように伝え方を工夫するようにしました。
この言い換えを瞬時にできるようになるまで、よく使うパターンを自分なりにストックしていきました。
問いの引き出しを増やす
これが一番大切にしていたことです。メンバーがテーマを設定していない時に、問いを工夫しないと「あ、大丈夫です」で終わってしまいます。
事象に対して本人も整理や言語化ができていないことも多々あるので、引き出すような問いをするようにしました。
具体的には、「○○の件、以前よりスムーズだったよね。何か工夫したこととかある?」と成長を実感させる問いかけや、「今回、何がよかったと思う?」「何か意識したポイントはある?」など成果を再現性につなげる問いかけを意識するようになりました。
良い問いを生み出すには、メンバーの仕事を深く理解し、事前に考える時間が必要でした。
感情にラベルをつける
頭では分かっていても気持ちの整理がつかないことってありますよね。
それを無視して諭すことはできますが、それが蓄積してしまうとメンバーはモヤモヤが吐き出せずメンタル不調につながったり、「もういいや」と自己完結してしまいます。
できるだけメンバーが良いコンディションで働けるよう、良い感情だけでなくよくない感情も一緒に向き合うようにしました。
「それはモヤモヤするよね」「悔しかったんだね」のように感情にラベルをつけることで、メンバー自身も自分の気持ちを客観視できるようになりました。
積み重ねが生んだ変化
これらの技術を地道に実践し続けた結果、徐々に変化が現れました。
メンバーが「整理できてないんですけど…」という状態で話を持ってきてくれるようになったんです。
「まだ言語化できてない」「こんなこと相談していいのか分からない」、そんな状態でも、私になら話してみようと思ってもらえる。この変化は大きな手応えでした。
さらに予想外だったのは、これらの技術が私自身のクライアントワークでも活きたこと。
問いの立て方、傾聴の技術、言い換えのスキル。すべてが「先方が本当に伝えたいことは何か」を引き出す武器になりました。
1on1は技術と実践の積み重ね
1on1は、必要な技術を身につけることで初めて価値ある時間になる。
もし過去の私と同じように1on1でモヤモヤしている人がいたら、以下のことを意識して臨むと良いかもしれません。
- 言い換えや問いを工夫して、メンバーが前向きな状態で終われる設計をする
- 解決策を提示するのではなく、メンバー自身が気づきに至るプロセスを支援する
- 1on1で話した内容を次回までに確実にフォローし、信頼の積み重ねをつくる
1on1に正解はありません。でも確実に言えるのは、手なりでやって上手くいくほど、1on1は簡単じゃない。
対話の技術を磨き、実践を重ねる努力なしに、良い1on1は生まれない。
これが、私が1on1を通じて学んだことです。