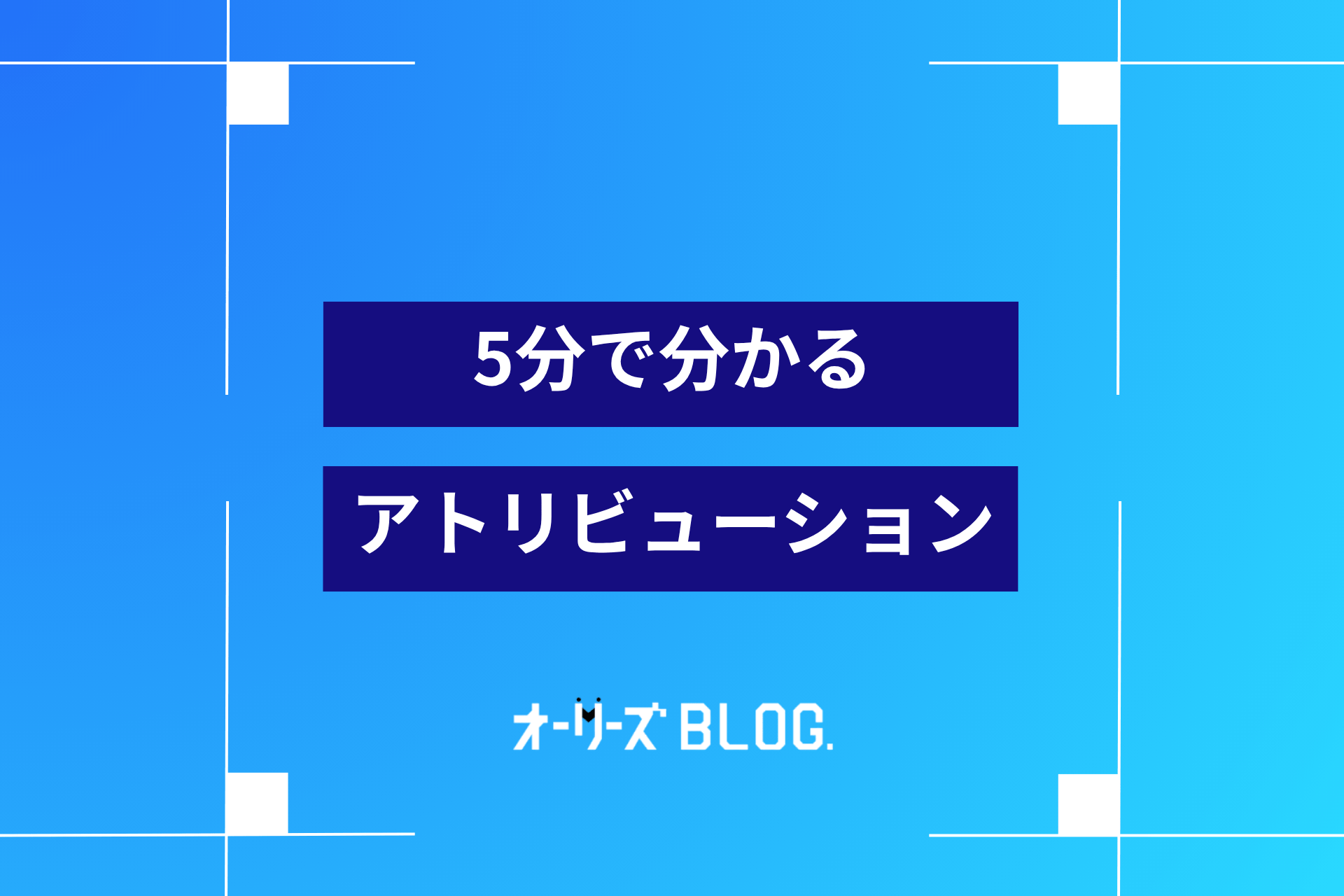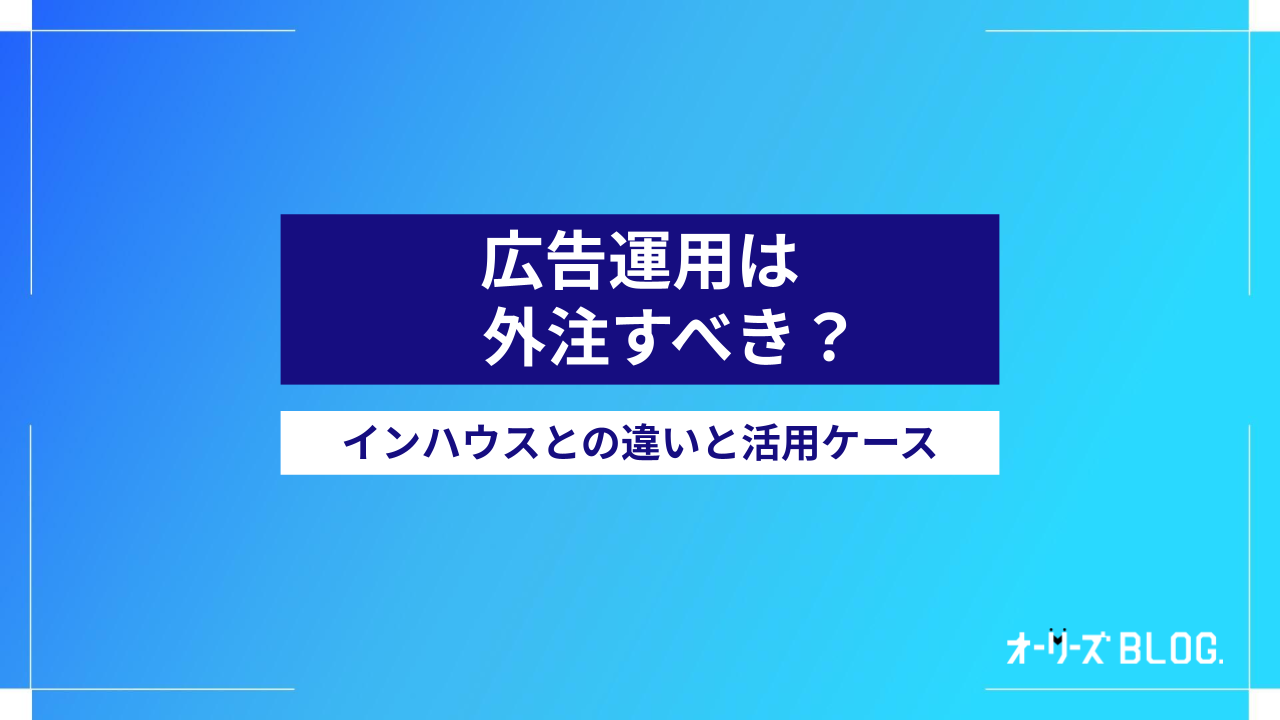- ナレッジ・ノウハウ
- 肥田 悟志
「配慮」は組織を強くするが、「遠慮」は組織を弱くする

ある1on1で、部下が「肥田さん忙しそうなので、1人で仕事を回せるように頑張ります」と話してくれました。
その言葉自体は前向きで嬉しいものでしたが、同時に、私への気遣いから”抱え込もうとしている”ようにも感じました。
私自身の立ち振る舞いが、知らず知らずのうちに「遠慮を生む空気」を作っていたのではないかと、私は自分のマネジメントを見直すことにしました。
気遣いが生んだ小さなすれ違い
当時の私は、複数のプロジェクトを同時に進めていて、常に予定が埋まっていました。
会議が続き、席を外すことも多かったため、周りから見れば「話しかけづらそう」に見えていたのかもしれません。
「声をかけようと思ったのですが、忙しそうだったので…」
「お手間を取らせないように、自分の判断で進めておきました」
「立て込んでいると思うので、後でまとめて共有しますね」
どれも私への気遣いから出た言葉です。優しさから遠慮をしてしまったのかもしれません。
私は自分の立ち振る舞いによってメンバーに遠慮をさせてしまったことを反省すると同時に、遠慮がチームの成長の芽を摘んでしまっているのではないかと感じるようになりました。
「配慮」はアクセル、「遠慮」はブレーキ
部下との会話をきっかけに、私は「配慮と遠慮は別物である」と考えるようになりました。
どちらも気遣いという点では共通していますが、結果に差があります。
「配慮」は、物事を前に進めるための気遣いです。相手が忙しそうでも、早めに共有・相談することで判断や行動を早めることが出来ます。
一方「遠慮」は、進むはずの物事を止めてしまう気遣いです。忙しさに気を配るあまり、共有や相談を先送りにすることで、判断や行動が後ろ倒しになります。
この違いが積み重なると、チーム力に差が生まれます。
遠慮が奪う「見えない損失」
遠慮が続くと、学びの機会が減ります。相談や壁打ちを通じて得られる気づきと、挑戦する機会が失われるからです。
成長は「考える → 試す →振り返る」の繰り返しで生まれます。相談や壁打ちは、成長を促すための重要なきっかけです。
しかし、遠慮によってそれを省いてしまうと、試行回数が減り、学びの機会も減る。結果として、意思決定の質も、改善のスピードも落ちてしまいます。これが、遠慮が生み出す見えない損失です。
そしてこの影響は、個人の範囲にとどまりません。チームはメンバーそれぞれの経験と学びの積み重ねで成り立っています。誰かが学びを止めれば、その分だけ組織全体の成長も減速してしまう。
だからこそ、遠慮をなくし、意見や相談が自然に行き交う状態をつくることが、結果的に組織の強さにつながるのだと思います。
「遠慮しないチーム」を作るために変えたこと
マネージャーの役割は、メンバーの挑戦を支え、成長を後押しすることです。相談や壁打ちを遠慮されると、その役割を十分に果たせなくなります。
また、メンバーにとっても、相談や壁打ちは自分の考えを整理し、学びを深める重要な機会です。それを失うことは、上司とメンバーの双方にとって「見えない損失」になります。
理想は、メンバーが自立して意思決定し、主体的に動ける状態ですが、その理想に至るまでには、対話と試行錯誤による学びが欠かせません。
私は、「遠慮しないチーム」を作るために自分の行動を変えました。
まず、言語化して伝える。
メンバーに遠慮させる空気を作らないためには、普段から「学びのために、遠慮をしないで欲しい」というメッセージを伝え続ける必要があります。
上司側が意図を言葉にして示さなければ、誤解は残ったままになるからです。この記事を書いているのも、その意図を共有するための一つの手段です。
そして、言行一致を徹底する。
言葉だけではなく、実際に相談を受けたときにどう行動するかが重要です。時間をとって話を聞き、もらった意見には真剣に向き合う。
そうした行動の積み重ねが、「このチームでは遠慮しなくていい」という信頼を育てていくと感じています。
配慮は手放さず、遠慮は捨てる
気遣いは、チームを円滑に動かすうえで欠かせないものです。ただ、それが「遠慮」に変わると、学びの機会を失わせてしまうことがあります。
上司は「忙しそうに見えること」がメッセージになるし、部下は「迷惑をかけないように」と行動を止めてしまう。 この小さなすれ違いを放置すれば、組織の成長は遅くなります。
だからこそ、配慮は大切に、遠慮は手放したい。
言葉にして伝え、行動で示し、安心して意見が交わせる環境をつくること。それが、組織を前に進める上司の役割だと感じています。