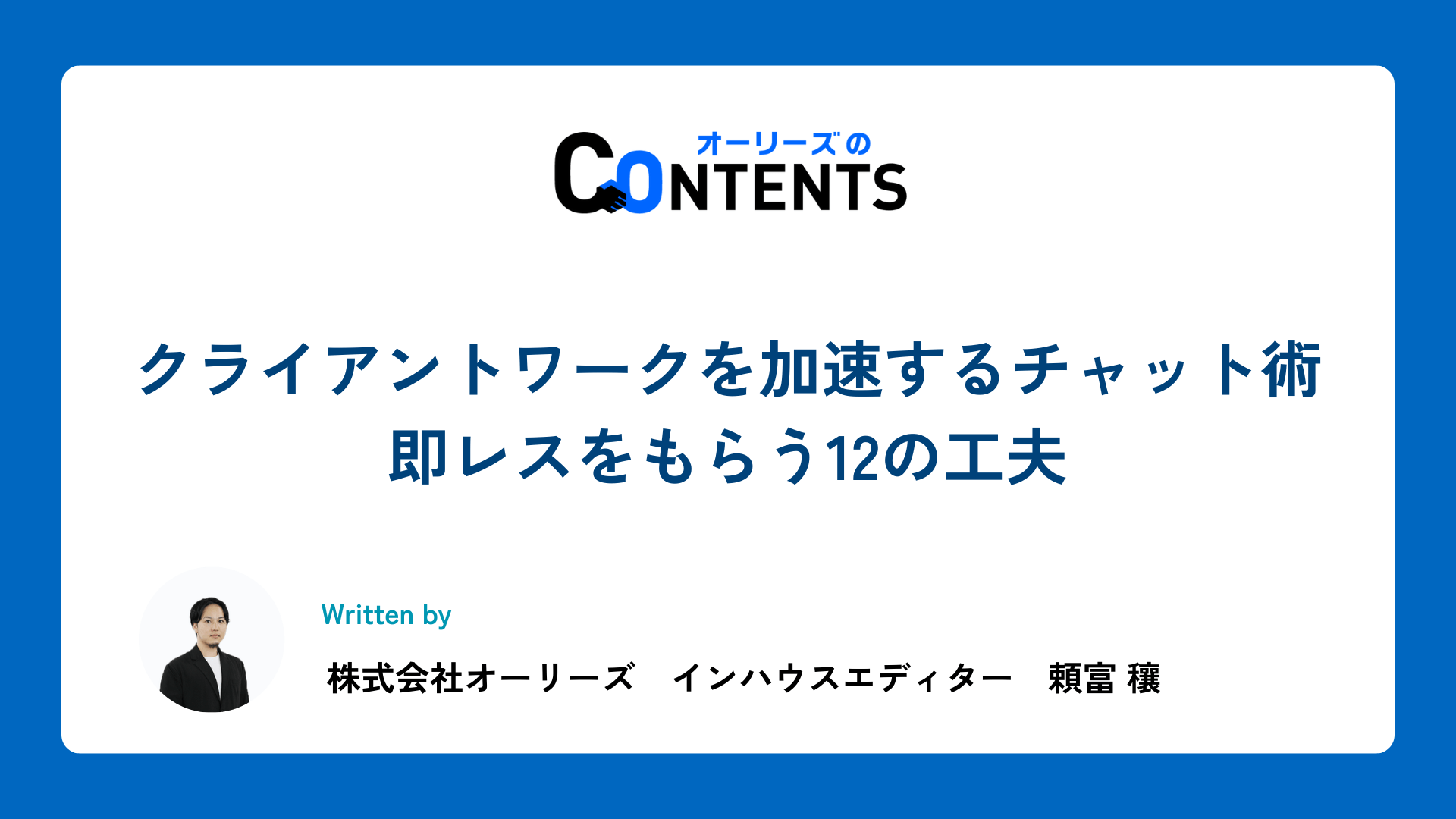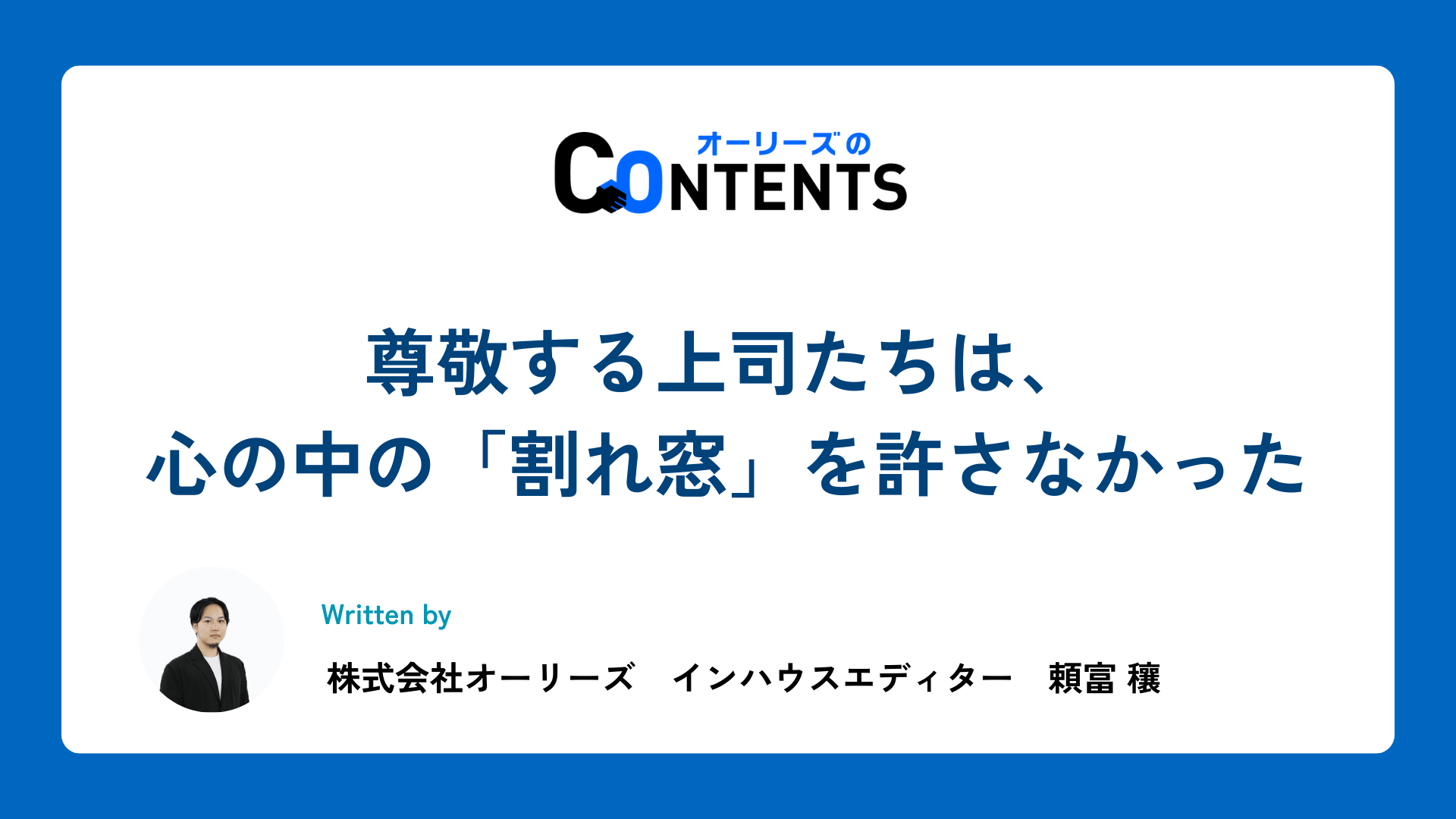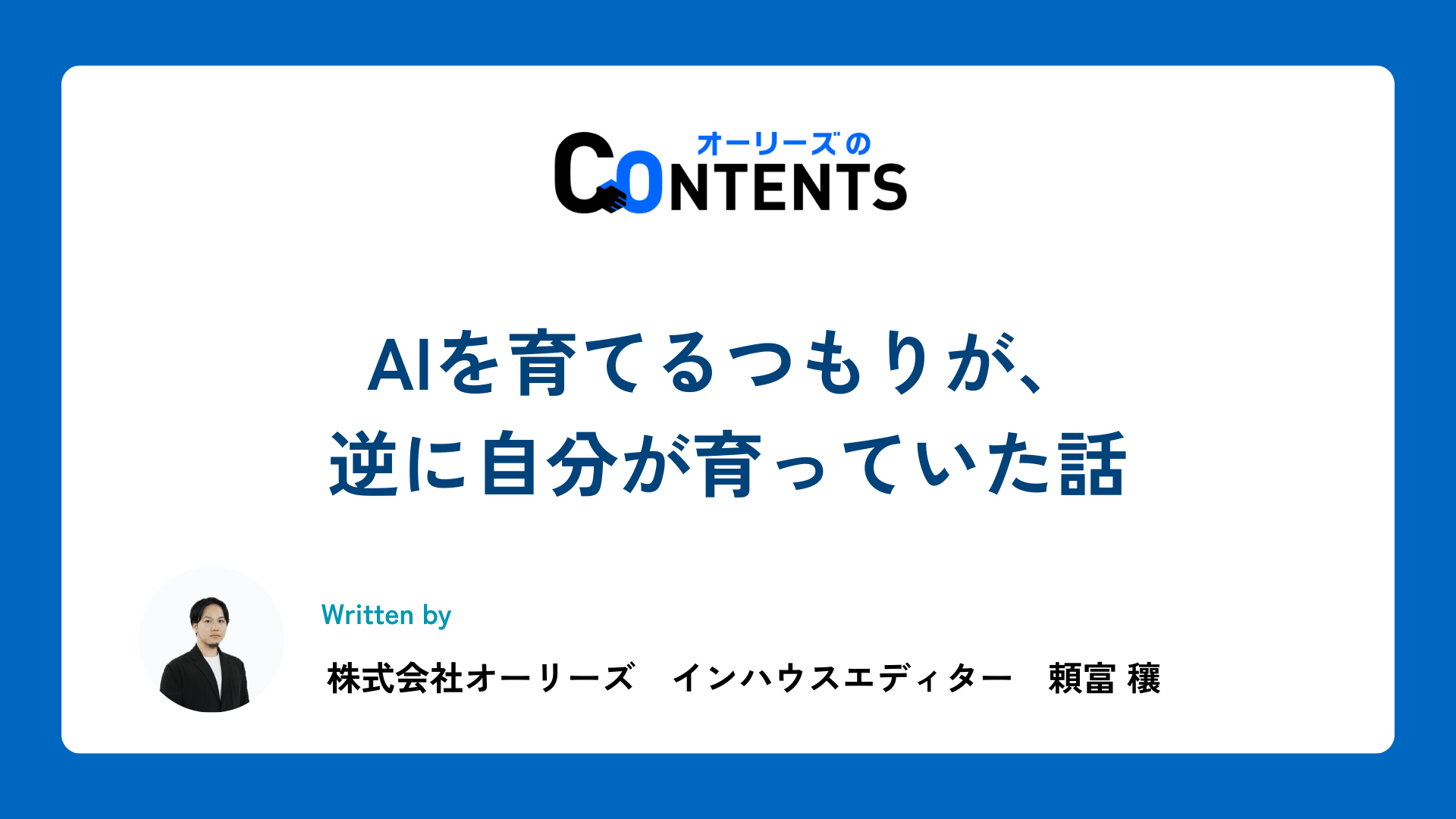- ナレッジ・ノウハウ
- 頼富 穰
リスティング広告とディスプレイ広告の違いとは?目的別の使い分けを解説
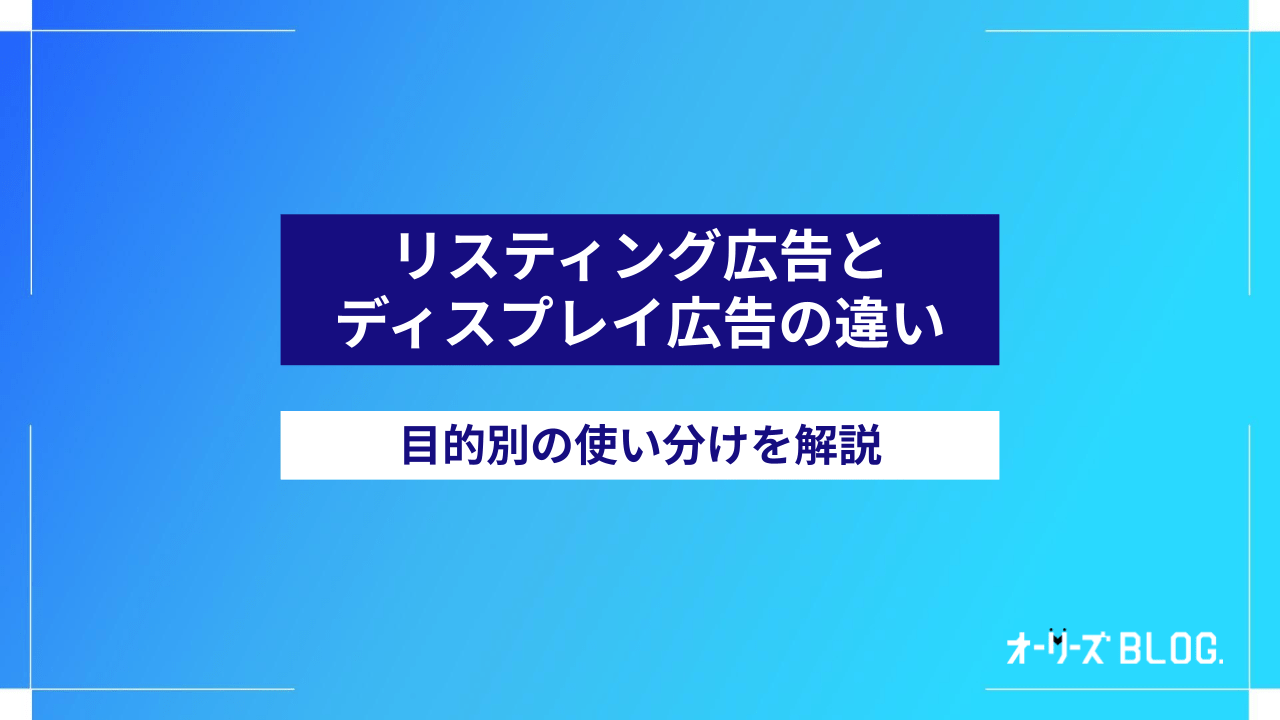
Web広告は、現代のマーケティング戦略において欠かせない要素となっています。中でも、リスティング広告とディスプレイ広告は、多くの企業が活用する代表的な手法です。
しかし、いざ広告を出稿しようとすると、
- 「リスティング広告とディスプレイ広告、具体的に何が違うの?」
- 「自社のサービスにはどちらの広告が向いているんだろう?」
- 「費用やターゲティングの方法はどう違うの?」
など、基本的な違いから目的別の使い分けまで、悩みを抱える方が多いことも事実です。
そこで本記事では、Web広告の担当者なら必ず押さえておきたいリスティング広告とディスプレイ広告の違いについて、図や表を交えながら分かりやすく解説します。
この記事を読めば、自社の目的に最適な広告手法を選択できるようになります。
リスティング広告の配信・運用で迷ったら
100社以上の支援実績がある「オーリーズ」へご相談ください
リスティング広告の配信・運用で迷ったら、100社以上の支援実績があるオーリーズへ
配信設計から運用まで、リスティング広告を起点に顧客の事業成長に貢献します。
【広告成果を最大化するオーリーズの特徴】
- 顧客の課題にコミットするため、担当社数は最大4社
- 運用者=顧客窓口だからスピーディーな仮説検証が可能
- 顧客の半数以上が「強く」おすすめしたいと評価
目次
ディスプレイ広告とリスティング広告の基本を解説
Web広告の代表的な手法として知られるディスプレイ広告とリスティング広告。どちらも企業のマーケティング活動で重要な役割を担いますが、その特性は大きく異なります。
それぞれの広告がどこに、どのような形式で表示されるのかを理解することが、効果的な広告戦略を立てるための第一歩です。
広告の掲載場所と表示形式の違い
ディスプレイ広告とリスティング広告の代表的な違いとして、広告の掲載場所と表示形式の違いがあります。
リスティング広告:検索結果にテキストで表示
リスティング広告は、GoogleやYahoo! JAPANといった検索エンジンの検索結果ページに表示される広告です。
ユーザーが特定のキーワードで検索した際、検索結果の上部や下部に「スポンサー(広告)」というラベルと共にテキスト形式で表示されます。
広告は主にURL、見出し、説明文で構成され、ユーザーの検索意図に直接応える情報提供に特化しています。
ディスプレイ広告:Webサイトやアプリに画像・動画で表示
一方、ディスプレイ広告はニュースサイトやブログ、個人のウェブサイト、スマートフォンのアプリなど、様々なウェブコンテンツの広告枠に表示されます。
テキストだけでなく、画像(バナー)や動画を用いて視覚的にアピールできる点が大きな特徴です。
ユーザーが特定の情報を探している時以外にも、Webサイトの閲覧中に広告を表示できるため、幅広い層へのアプローチが可能です。
潜在的な顧客に自社の製品やサービスを認知してもらうきっかけ作りに適しています。
【比較表】ディスプレイ広告とリスティング広告の違い
ディスプレイ広告とリスティング広告の違いについて、ポイントをまとめた比較表を作成しました。
| 項目 | リスティング広告 | ディスプレイ広告 |
|---|---|---|
| 掲載場所 | 検索エンジンの検索結果ページ | Webサイト、アプリ内の広告枠 |
| 広告形式 | テキスト | 画像、動画、テキスト |
| アプローチ層 | 顕在層(ニーズが明確) | 潜在層(ニーズが不明確) |
| 主な目的 | コンバージョン獲得 | 認知拡大、ブランディング |
| 課金形態 | 主にクリック課金(CPC) | クリック課金(CPC)、インプレッション課金(CPM) |
| ターゲティング | 検索キーワード | ユーザー属性、興味関心、サイト訪問履歴など |
【目的別】どちらの広告を選ぶべきか
広告戦略を立てる上で最も重要なのは、「誰に、何を伝え、どうなってほしいか」という目的の明確化です。
リスティング広告とディスプレイ広告は得意な領域が異なるため、自社の目的がコンバージョン獲得なのか、認知拡大なのかによって、選ぶべき広告手法も変わります。
コンバージョン獲得が目的ならリスティング広告
商品購入や問い合わせといった、ユーザーの具体的なアクション(コンバージョン)を直接の目的とする場合、リスティング広告が非常に有効です。
顕在層に直接アプローチできる
リスティング広告の最大の強みは、商品やサービスを「まさに今、探している」ユーザーに広告を表示できる点にあります。
例えば、「ランニングシューズ おすすめ」と検索するユーザーは、ランニングシューズの購入を検討している可能性が非常に高いでしょう。
このような購買意欲の高い「顕在層」へ直接アプローチできるため、他の広告手法に比べてコンバージョンに結びつきやすいのが特徴です。
費用対効果を測定しやすい
リスティング広告は、クリック数やコンバージョン数といった具体的な数値データを詳細に取得でき、費用対効果の測定が容易です。
どのキーワードがどれだけの成果につながったかを分析し、予算配分や入札単価を細かく調整することで、継続的な広告効果の改善が可能です。
PDCAサイクルを回しながら広告運用を最適化したい場合に適しています。
認知拡大が目的ならディスプレイ広告
新しいブランドの立ち上げや新商品のリリース時に、まずは多くの人に存在を知ってもらいたいという「認知拡大」が目的であれば、ディスプレイ広告が力を発揮します。
潜在層に幅広くアプローチできる
ディスプレイ広告は、提携する多数のWebサイトやアプリに広告を掲載できるため、非常に広範囲のユーザーにリーチできます。
まだ自社の製品やサービスを知らない、あるいは特にニーズを感じていない「潜在層」に対し、視覚的なインパクトで興味を喚起し、新たな顧客層を掘り起こすきっかけを作ります。
リターゲティングで再訪を促せる
一度自社のサイトを訪れたものの購入や問い合わせには至らなかったユーザーを追跡し、別のサイトを閲覧中に再度広告を表示する「リターゲティング(リマーケティング)」機能もディスプレイ広告の大きな武器です。
繰り返しアプローチすることで自社ブランドを思い出してもらい、再検討を促す効果が期待できます。
ターゲティングと費用の違い
広告の成果を最大化するためには、誰に広告を見せるかという「ターゲティング」と、どれくらいの費用をかけるかという「予算管理」が鍵となります。
リスティング広告とディスプレイ広告では、これらの考え方や手法が大きく異なります。
ターゲティング手法の違い
まずは両者のターゲティング手法の違いです。
リスティング広告:検索キーワードでターゲティング
リスティング広告のターゲティングは、ユーザーが検索窓に打ち込む「検索キーワード」が基本です。
広告主は自社の製品やサービスに関連するキーワードを指定し、そのキーワードで検索したユーザーに広告を表示します。
ユーザーの検索意図そのものを捉えるため、非常に精度の高いターゲティングが可能です。その他、地域や曜日、時間帯、使用デバイスなどで配信対象を絞り込むこともできます。
ディスプレイ広告:ユーザーの属性や興味関心でターゲティング
ディスプレイ広告は、より多角的なターゲティングが可能です。年齢、性別、地域といった基本的なデモグラフィック情報に加え、ユーザーが過去に閲覧したサイトの傾向から「興味関心」を推測してターゲティングしたり、特定のテーマのサイトを指定して広告を配信したりできます。
前述の「リターゲティング」もこのターゲティング手法の一つです。幅広いデータに基づき、様々な切り口でターゲット層にアプローチできるのが強みです。
費用と課金形態の違い
次に、両者の費用と課金形態の違いです。
リスティング広告:クリック課金が中心
リスティング広告の費用は、主に広告がクリックされるごとに課金される「クリック課金」が採用されています。
広告が表示されるだけでは費用は発生せず、ユーザーが興味を持ってクリックしサイトに訪れた時点で初めて費用が発生するため、無駄な広告費を抑えやすいメリットがあります。
クリック単価は、キーワードの人気度や競合の多さによって変動するオークション形式で決まります。
ディスプレイ広告:クリック課金とインプレッション課金
ディスプレイ広告では、クリック課金に加え、広告が1,000回表示されるごとに課金される「インプレッション課金」も広く利用されています。
認知拡大が目的で、とにかく多くのユーザーに広告を見てもらいたい場合には、CPMの方が費用対効果は高くなることがあります。
どちらの課金形態を選ぶかは、広告の目的によって慎重に判断する必要があります。
運用でよくある失敗と対策
広告運用は、設定して終わりではありません。効果を最大化するには、日々のデータ分析と改善が不可欠です。
ここでは、特にディスプレイ広告とリスティング広告の運用で陥りがちな失敗例とその対策を解説します。
ディスプレイ広告で注意すべき「意図しないクリック」
ディスプレイ広告はWebサイトのコンテンツに溶け込むように表示されるため、ユーザーが誤ってクリックしてしまうことがあります。
特にゲームアプリの広告などで、操作ボタンの近くに広告が表示されるケースが典型的です。このような意図しないクリックが増加すると、コンバージョンにつながらない無駄な広告費が発生してしまいます。
対策として、広告の配信先(プレースメント)を定期的にチェックし、クリック率が異常に高いにもかかわらず成果が出ていないサイトやアプリを除外設定することが重要です。
リスティング広告で陥りがちな「予算の浪費」
リスティング広告では、キーワードの選定が成果を大きく左右します。
しかし、関連性の低いキーワードや、検索ボリュームが大きすぎる一般的なキーワード(例:「広告」など)にまで広告を出稿すると、コンバージョン意欲の低いユーザーからのクリックが増え、予算を早期に消化してしまうことがあります。
この事態を防ぐためには、自社のサービスと関連性の高い具体的なキーワードに絞り込むこと、そして「無料」「とは」といったコンバージョンに繋がりにくい語句を「除外キーワード」として設定し、無駄な広告表示を防ぐことが効果的です。
ディスプレイ広告とリスティング広告の連携で効果を最大化する
リスティング広告とディスプレイ広告は、それぞれ単体で活用するだけでなく、戦略的に連携させることで弱点を補い合い、相乗効果を生み出せます。
両手法を組み合わせるメリット
最大のメリットは、潜在層から顕在層まで、顧客の検討段階に応じて一気通貫でアプローチできる点です。
まずディスプレイ広告で幅広い潜在層に自社サービスを認知させ、興味を持ったユーザーが検索行動を起こした際にリスティング広告で確実に受け止めコンバージョンに繋げる、という理想的な流れを構築できます。
具体的な連携戦略
具体的な戦略として、まずディスプレイ広告のリターゲティング機能を活用し、一度サイトを訪れたユーザーに継続的にアプローチします。
同時に、そのユーザーが比較検討段階で検索しそうなキーワード(競合製品名や「〇〇 比較」など)に対してリスティング広告を出稿しておけば、取りこぼしを防げます。
さらに、リスティング広告の検索語句レポートを分析してユーザーが実際に使用しているニーズの高いキーワードを発見したら、そのキーワードをテーマにしたディスプレイ広告のクリエイティブを作成し、新たな潜在層にアプローチするというサイクルを回していくと効果的です。
まとめ|目的を明確にして最適な広告を選ぼう
本記事では、リスティング広告とディスプレイ広告の基本的な違いから、目的別の使い分け、運用上の注意点、そして両者を連携させる戦略までを解説しました。
重要なのはどちらの広告が優れているかではなく、自社のマーケティング目的を明確にし、それぞれの広告の特性を最大限に活かすことです。
- 購買意欲の高い顧客にアプローチしたいならリスティング広告
- ブランドの認知度を高め、将来の顧客を育てたいならディスプレイ広告
まずはこの基本を抑え、自社の状況に合わせて最適な広告手法を選択し、効果的なWebマーケティングを実現してください。
リスティング広告の成果改善なら「オーリーズ」
顧客の半数以上が強くおすすめする広告代理店
リスティング広告の成果改善でお悩みなら、100社以上の支援実績があるオーリーズへ
運用改善から戦略提案まで、リスティング広告を起点に顧客の事業成長に貢献します。
【広告成果を最大化するオーリーズの特徴】
- 顧客の課題にコミットするため、担当社数は最大4社
- 運用者=顧客窓口だからスピーディーな仮説検証が可能
- 顧客の半数以上が「強く」おすすめしたいと評価